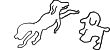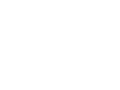Research vol.6
看護師 菊池郁希
医療従事者は泣いちゃいけない、感情移入しちゃいけない、ということはない。ベースは「人と人」。事実は何で、それを誰がどう解釈していてどういう感情を持っているのか、それをきちんと分かっていることが大事。
《きゅうかくうしお的醸す》プロジェクトの醸す人リサーチvol.6は、看護師の菊池郁希さん。青年海外協力隊として赴任したパラグアイでの活動などを経て、現在は軽井沢の診療所「ほっちのロッヂ」の訪問看護ステーションの管理者も務める菊池さんに、人の死に直面する機会も多い、医療の最前線に立つ看護師の視点での「醸す」を聞く。
2022.1.9 SUN TEXT BY JUNKO YANO

映像
自立したメンバーが話し合いながらやってる
ー 自分的にはそんなに余白なく働いてるけど、どう付き合ってどう働きたいか、という話をみんなでしている。開業から2年、人数も10人くらいで年も近いから仲間感が生まれやすいという環境も大きいけど、とにかく話している。

ー ここでは誰かに頼るとかはなく、自分たちで考えて動いて、全員がチャレンジしている。最適解が何かは分からないけど、一生懸命考えて出した答えでやって、間違えるかもしれないけどやる、という感じ。医療は上下関係の世界。経験がモノを言うところもあるので、経験者に相談したり、私たち看護師が医師の資格を持ってる人たちに判断を仰ぐ部分はあるけど、お互いそれをひけらかさずやっている。

ほっちのロッヂ共同代表
ー ここに入りたい人も、それが大事だと思ってるから来てる。
映像 松澤
青年海外協力隊でパラグアイへ
ー 東京の病院に勤めた後、青年海外協力隊の看護師枠でパラグアイに2年間行っていた。「保健ポスト」という村の診療所が勤務先で、村の人たちに保健教育をする活動をしていた。
国によるけど、パラグアイでは日本から派遣されたスタッフによる医療行為は行えない。風邪ひいた時やちょっと手を切ってしまった時の手当てをしたり、予防接種対応、妊婦健診など。あと診療所の待ち合いや学校、地域での予防啓発などを担当していた。
宣伝美術 矢野
ー 言葉は、スペイン語と現地語のグアラニー語を混ぜて使っていた。
専門用語を使った医療行為の説明とかではなく「なぜ野菜食べるといいか」「塩がどう血圧に関係するか」など、暮らしの改善についての話をしていた。
私は2年で居なくなるから現地スタッフができるようになった方が良いので、ひとりでやらずに「自分はこういうことをやりたいんだけど、手伝ってくれる?」と、一緒にやっていた。
宣伝美術 矢野
「ホームステイ先のママ」と「とにかく言葉にすること」で広がった交流
ー 現地で活動するにあたって「自分はこんな人間であり、敵ではない」という事を分かってもらいたかった。
ホームステイ先のママが本当に良い人で、村を一緒に歩くというところから始めて、村の道がどうなっているか、すれ違う人とどんな挨拶をしたらよいかを教えてくれた。職場の診療所の人たちと繋げてくれたり、ステイ先に来客があるたびに紹介してもらった。

ー あとは、言葉が分からないなりに「自分はこうしたい、何かをしたい、困っている」をとにかく話していた。それを続けるうちに、自分の思考ややりたいことを汲んでくれるようになり、それが広がっていった。
映像 松澤
外国人として異文化の中で過ごした経験が今に生きている
ー 「やりたい」と言う事は大事。パラグアイでの体験が私の今をつくっていると最近よく思う。
外国人として異文化圏で過ごしたことで、「自分は元々社交的なタイプだけど言葉が分からないと消極的になるんだ」「言葉も文化も分からない場所で過ごす時は周りにこうしてもらえたら嬉しいな」「単純作業なら言葉が分からなくてもできる、作業していれば何かの役には立っていると思えるんだ」といった気づきがあって、それらが今生かされている。
宣伝美術 矢野
北海道で出会った訪問看護と、探していた仕事仲間
ー 地域で働くのも楽しそうだなと思っていて、帰国後に「国際」と「地域」の両方をやれないか探していたら、北海道のとある病院が「地域の病院に勤めながら、1年のうち1ヶ月は国内外の好きな研修に行ける」というプログラムをやっているのを見つけて北海道に行った。
タイミングが合わずそのプログラムで海外に行くことはなかったけど、北海道で訪問看護に出会い、この人の元で働きたいと思う人との出会いもあった。
ー そんな中で、私の居たい場所はどこだろうと考えていた。また海外に行く事は今も思ってるけど、地域で自分の力を使おうとした時、家族や友人が近くに居て自然もあるところって、地元の長野でいいじゃんとなった。
同時に、ベテランの人たちに頼ってしまっていた自分への課題感もあった。もっと歳が近くて意見を出し合える仲間と働きたいと思っていたら、勤務先の訪問看護ステーションの管理者の方がここができることを知っていて、場所もやろうとしていることもこれだと思って繋げてもらって、2020年春にここに来た。

ー パラグアイと北海道の経験から、自分がどういう環境で働いていきたいか、自分の人生において仕事とはただお金を得るためのものではなく、自分のライフワークにも重なるように生きていくのが幸せだと感じていた。好きなことをして、人と関わり合いながらいられたらいいなと思い、その時はそういうキーワードだけでここに来た。
宣伝美術 矢野
想定していなかった管理者の仕事
ー 今看護ステーションの管理者もやっていること。いくつものことを並行で行う複雑さや忙しさと同時に、私はこれが好きなんだとも感じている。
当初はもっと軽いノリで来ていて、訪問看護ステーションの管理者は、ある程度の経験がないとできないすごい人という像が私の中にはあって、そんな人にはなれないと管理者を依頼されたときから思っている。でもそうなれなくも、一緒に考えて作り上げていく人たちが常に隣にいる。話し合って共鳴して何か出てきて、もちろんぶつかることもある。
ー 惰性で仕事をする人はひとりもいなくて、それが当然である中に居たいと思うけど、必ずしもそういう環境で働き続けられるわけではないと思っているから、その点は本当にいいな、と思っている。一緒に乗り越えてきてる感はある。
映像 松澤
自分の価値観を押し付けないこと
ー パラグアイに居た時と変わらないけど、自分の価値観を人に押し付けないこと。その良し悪しを判断しているのは自分だけだと思うようにしている。自分がどうにかしてやろうとは思わない。

「薬が出されてるから飲め」と指導することじゃなく、「その人がやりたいことをするために、なぜこの薬が大切か」を伝えることを大切にしたい。
もしその人が自らの意思で薬を飲まず、その方が本人の望む生活ができるのであれば、それを応援する。全てその人が決めること。
映像 松澤
ー ここにきて確信に変わった。それが普通だと思えるようになった。
パラグアイに行く前に5年間病院で働いていた。病院の看護はやるべきことが決まっていて、治療の場だからそれを遂行するのも大切なこと。
ただ、その治療を受けることに納得している人が患者として来ているのか、その深掘りはできていなかった。そういうベルトに乗せられた人たちが来ていたので、そこに向き合えてなかった。
教育体制のしっかりした東京の病院だったけど、ここに来て思えば甘かったなと思う。

映像 松澤
ー そうかもしれない。それを掲げた方が楽なんじゃないか、何に向かってるんだろうか、って思うこともあるし、思う方向はそれぞれかもしれないけど。共同代表の紅谷さんも「決めないことだけは決めてる」とよく言っている。
宣伝美術 矢野
共通の達成感を味わうことは大切
ー バラバラなところもある。向き合っている訪問先の人に対してなら「なんでこの人はこう考えるんだろう」って思えても、隣の人にはそう思えないことはある。ずっとそうなわけでもないけど。
ー これはやって良かったという共通の達成感を味わうことは大切かも。やったね、良かったね、そういうポジティブな共有を大切にする。うちの中も良いことばかりではない。人の生き死にもある場所なので。
宣伝美術 矢野
死は尊くて日常にあるもの
ー 毎回悲しいし、もっとこうできたのにと思う。すごい尊いものでもあるし、でも日常の一部であって遠くの特別なことではない。
「人は生きて、人は死ぬんだ」と思っている。
昭和の時代から病院がたくさんできて、最期の場所は病院ということも多くなり、亡くなることが遠くになってしまった。でも死は近くにあるもの。
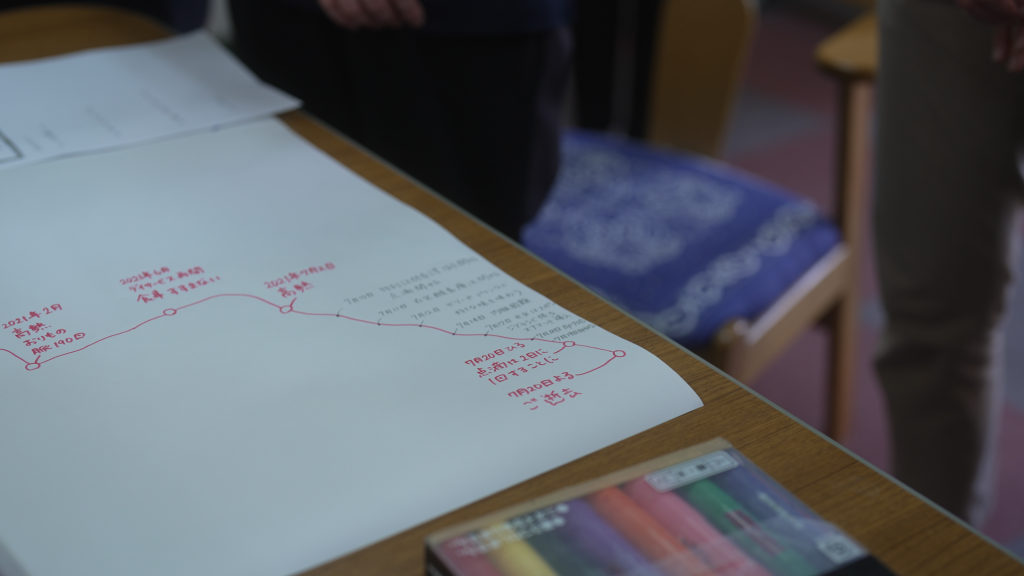
ー 以前、看ていた方が早朝に亡くなり、旅立ちの支度を整えていた。そんな日であっても、朝は来て人はお腹が空く。亡くなった方の着替えをしている傍らで、水道から水が流れる音、やかんが沸騰する音、朝ご飯を温める音、看取りに来たドクターのお子さんが話す声、いろんな音が聞こえる。そういうたくさんの日常の音の中に「死」もある。死は、人が生まれてくるのと同じく、日常から離れていないということ。
死にもいろんな瞬間がある。息を引き取った後に行くことが多いけど、最期の時を一緒に居て欲しいと言われて行くこともある。それを重ねている。
宣伝美術 矢野
「どう生き切るか」を何度も確認して真意を想像する
ー 親しんだベッドや音があるのが家。病院は、カーテンで仕切られた中に泊まることを許された家族がひとりだけ隣にいて、モニターやいろんなものに繋がれて心電図の音が鳴っている空間。
でも家だけが全てではない。家で死を迎えたくないという方もいる。それは「どう死ぬか」というより「どう生き切るか」で、何回も確認する。絶対迷うし気持ちは変わるから。

「絶対家で」と思っている人が「やっぱり無理」となって病院を選んだり、その逆もある。
だから、発する言葉だけでなくその裏にある真意を、それまでの関わりの中から想像できるようにいたい。そこは課題というか、そういたいと全員思っている。
宣伝美術 矢野
ここでは自分の感情を大切にして良い
ー 短い問診の中ではそう感じるかもしれないけど、裏ではそうでもないこともある。あの外来の患者さんどうしようって話してることもある。でもそういうのは表に出してはいけないという教育を受けている。
ー 特に病院だとそうなるかも。でもここでは気持ちを大事にしていい。医療従事者は泣いちゃいけない、感情移入しちゃいけない、こうあらねばいけない、ということはない。結局ベースは「人と人」。自分を構成している要素のひとつに看護師という要素があるだけ。

ー ほっちのロッヂを運営する医療法人社団オレンジの考え方で、「自分の感情にフォーカスを当てる」というのがある。「そう思っているのは誰なんだ」と。
「事実は何で、そこから誰がどう解釈していて、どういう感情を持っているのか」にフォーカスを当てている。良い悪いは無く、それをちゃんと分かっていることが大事。
かわいそう・何かしてあげたい、と思うことは事実で、それは悪いことではない。でもそう思っているのは自分ですよね、それをやって欲しい・自分はかわいそうって本人は思ってるんですかね、という。
映像 松澤
違うことが許される場所
ー 今話しているのが私なので、こういう話しをしているけど、聞く人によって答えは違うと思う。それが許される場所でもある。
その人の言い方によっては自分は賛同できないこともある。あまりにも気になったら「その言い方だと私はこう思う」と伝える。その人を否定するのでなく「表出された部分に関して私はこう思った」という話し方をすることを大切にしている。
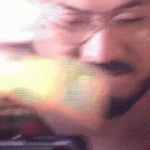
映像

宣伝美術
 今回の醸す人 菊池郁希(看護師)
今回の醸す人 菊池郁希(看護師)
長野県出身。看護師として東京都内の病院に勤務後、青年海外協力隊として南米パラグアイで2年間活動。村民の食生活改善指導を行う。帰国後、北海道での訪問看護を経て、2020年よりほっちのロッヂ(長野県軽井沢町)の訪問看護ステーションに勤務。地域看護師として訪問看護にあたると同時に、看護ステーション管理者も務める。